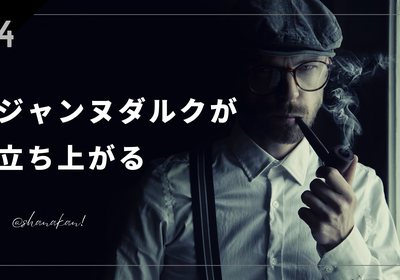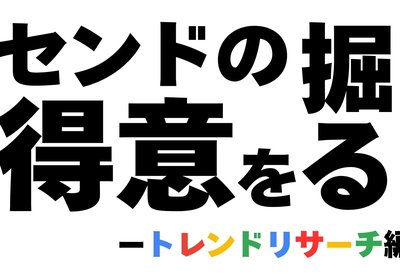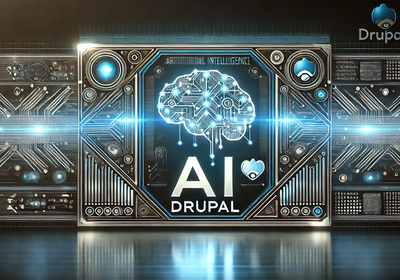きょうで令和となる5月1日まで10日を切りました。
万葉集に収められた文言
「初春の令月にして(しょしゅんのれいげつにして)、気淑く風和ぎ(きよく かぜやわらぎ)、梅は鏡前の粉を披き(うめは きょうぜんのこをひらき)、蘭は珮後の香を薫ず(らんは はいごのこうをくんず)」を引用し、
「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」
という意味が込められたそうです。西暦700年くらいの話だそうです。
この歌と関係深い太宰府にはこの発表後、訪れる人が増えているそうですね。
いつも通勤していますと、ふと興味が。

会社から最寄り駅である「薬院」にも太宰府同様に歴史はあるでしょうが
多くの方々が行き交う駅という知識しかありませんのでネットで確認してみました。
この地を薬院と呼ぶきっかけとなったのは
「施薬院」( やくいん、"せ"は省略し読まれる )という病人を薬で介抱する施設が造られた事からでした( 西暦700年くらい )。
聖徳太子が慈悲の思想に基づき、関西に造られたことが初めだそうです。
福岡のこの地に作った人物は、キビノマキビさんという方でした。
豪族出身であり大臣まで出世した人物で、菅原道真と同じくらい優秀な人だったそうです。
この人、岡山県あたりの出身でして
岡山と福岡の関係といえば、有名なお話らしいですが( 都市伝説くらいに思っていました )
「福岡」は岡山県、長船町福岡( おかさねちょうふくおか )というとある地名を黒田長政が引用し、城を福岡城、城下町は福岡としたことから呼ばれ始めたんだそうです。黒田の出身はこの" 長船町福岡 "だったんですね!!
なぜ黒田に名付ける権利があったかと言うと、関ケ原の戦いの戦果として徳川側から黒田にこの国が与えられたからだそうです。戦果としてというこの部分、ロマン感じます。( ここを一切知らないなら、福岡による岡山パクリ感が引っかかってしまう )
福岡移住組としては、福岡は色んなモノがある街という認識でありそれ以上の愛着を持っておりませんでした。ですが、少しでも歴史を知ることで日常の見え方、認識が変わることがあるなと感じました。
次回は僕が好きな豚骨ラーメンレポートでも書いてみます
まだ夜は冷えますので、お体ご自愛下さいませ